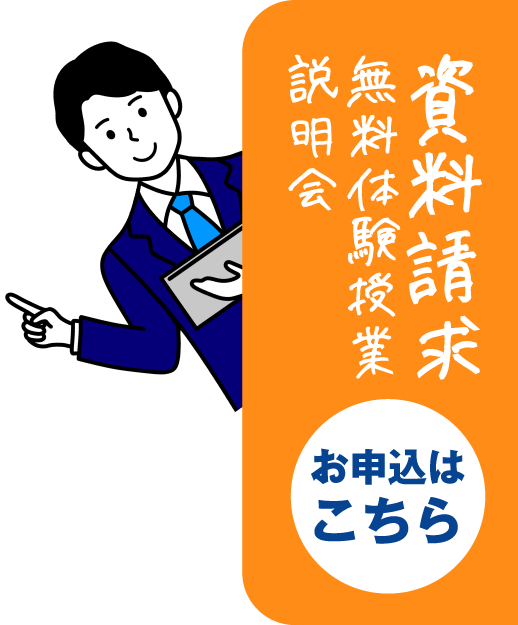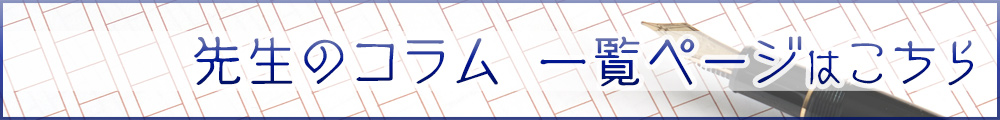- 先日、高校生用の教科書検定についての記事が新聞に掲載されておりました。興味がありましたので、いくつかの新聞なども比べて読んでみました。
特に国語の教科書に関して、ぼくが感じましたのは、新しさと古さ、その二つのよさと、そのあいだにあるものへの思いです。 - 国語の教科書で採用されている作家、作品は大きく分けて、いわゆる定番なものと、現在活躍中の作家に分かれるようです。定番とは、古典はもちろんのこと、夏目漱石、森鴎外、中島敦といった作家たち、新しい作家としてはよしもとばなな、江国香織、山田詠美といった主に女性の作家だそうです。ある教科書は、古典の比率が10パーセント近く増えているといった記述もありました。
- 古典文学のよさ、近代文学のおもしろさ、そして、現代の物語を読むこと、それぞれどれも必要であり、教科書に載っているべきものだと思います。
しかし、その一方で、教科書からなくなってしまう、減っていってしまう作家もいます。川端康成、井伏鱒二の作品は、だんだん少なくなり、谷崎潤一郎は四年前から掲載がなく、今回、吉行淳之介、開高健の作品が掲載されなくなったそうです。明治大正やそれ以前の作品よりもむしろ昭和に活躍した作家の作品の方が、かえって高校生たちには時代背景が読み取りにくく感じられるのではないか、なので減ってきているのではないか、と新聞には書かれていました。 - 教科書で学ぶことが国語の全てではありません。開高健、吉行淳之介の作品も、ぼくが実際に読んだのは高校を卒業してからずいぶんたった後です。高校生のときにもし読んだとしても、ぼくが楽しめたかどうかは、ちょっとわからないとも思います。教科書に載せられる作品は自ずから限られてしまいますから、どのような作品を選んだとしても完璧なものにはなりえません。ただ、なんともいえずさみしさを感じたこともまた事実です。結局、どの作品が選ばれ、そして選ばれなくなっても、同じことを感じるとは思うのですが……。なにかのときに教科書という形だけではなく、もっと違う形で本のおもしろさをみんなに教えることができたら、と思いました。
。
NEWS青葉台校室長
三木 裕