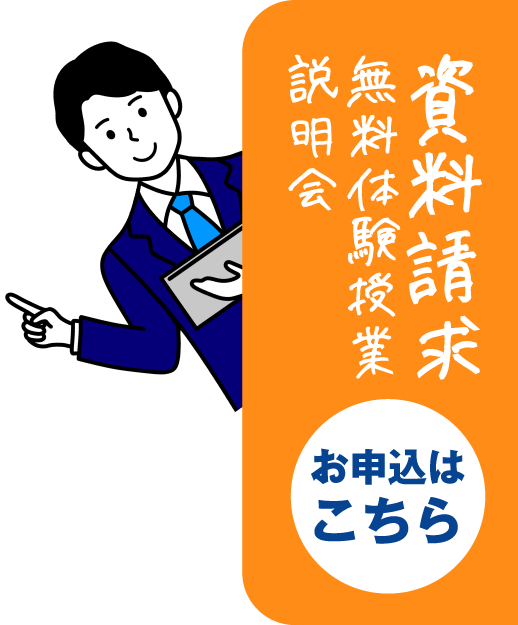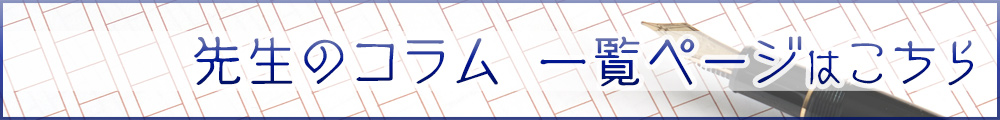- 前のコラムでも取り上げた本なのですが三宅泰雄「空気の発見」という本に著者のこんなあとがきが載っています。
『私は、科学教育が科学史とむすびついてなされることを、かねがね主張している。科学的精神をふきこむといっても、科学を創造した人々の思想や生活に、ふれずして、とうていその真髄を理解することはできないだろう。また、私は、科学教育は記憶を重んずるつめ込み主義ではなく、科学の発展してきた論理を生徒に理解せしめることに重点をおかねばならないと考えている。』
たしかにこの本では、空気という名前がついたところから始まり、有名な科学者だけではなく、当時はほとんど無視されていましたが、実は重要なきっかけとなることを発見した科学者たちのこともしっかりと書かれていて、読み物としてのおもしろさも十分に楽しめました。なかなか普段の授業ではここまで教えることは難しいと思いますが、この著者の主張は、実際にこの本という実践例もあり説得力があります。
必要なことはたしかにしっかりと記憶してもらわなければなりません。ただ、そのためには、それらの知識が単なる記憶するためだけの知識ではならないということなのでしょう。一見冷たく見える化学式にも、その発見には生きた人間の思い、努力、夢がありました。その思いを通して学んだ知識は、きっと子ども達の心に残る知識となり、そして、それだからこそ、それを次につなげる知恵へとつながっていくのではないでしょうか。もちろん、科学だけのことではないですね。NEWSは様々なコースがあり、いろいろな先生がいて、数え切れないほどの思いがあります。自分が教えていることに、きちんと思いは入っているでしょうか。ぼくは、なぜ作文の先生になったのでしょう。それは、思いを伝えるためでした……。そのはじめの気持ちを、あらためて考えてみようと思いました。
NEWS青葉台校室長
三木 裕